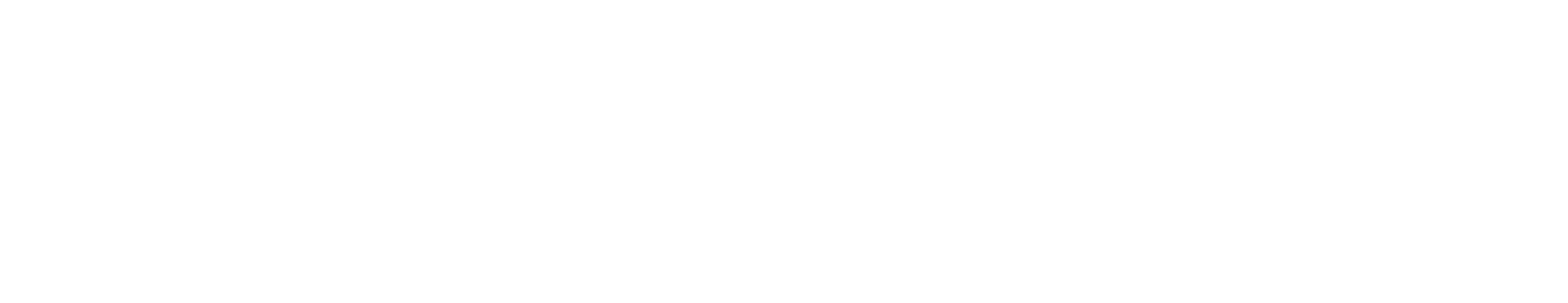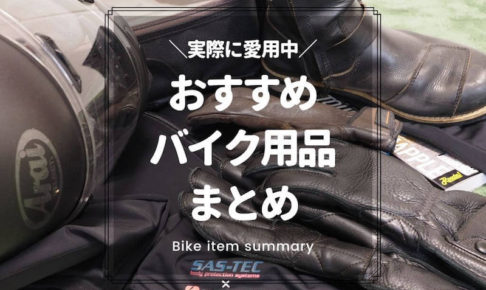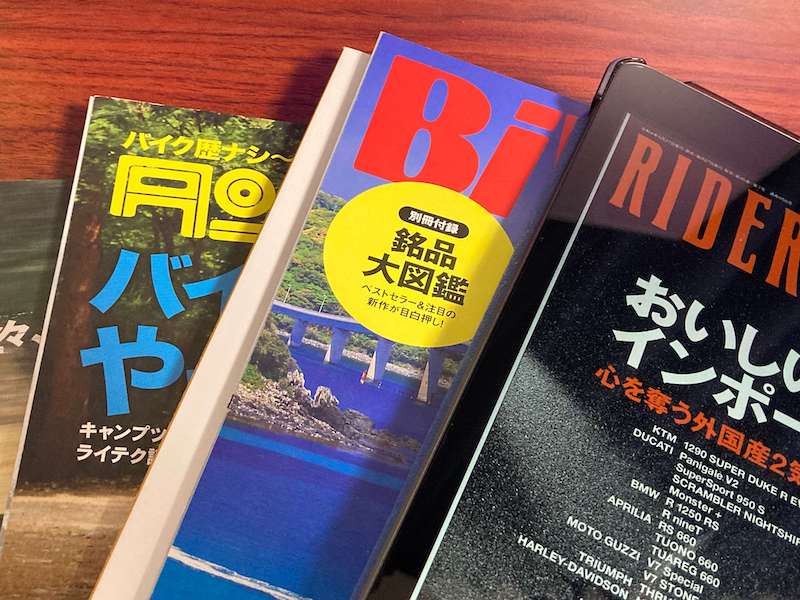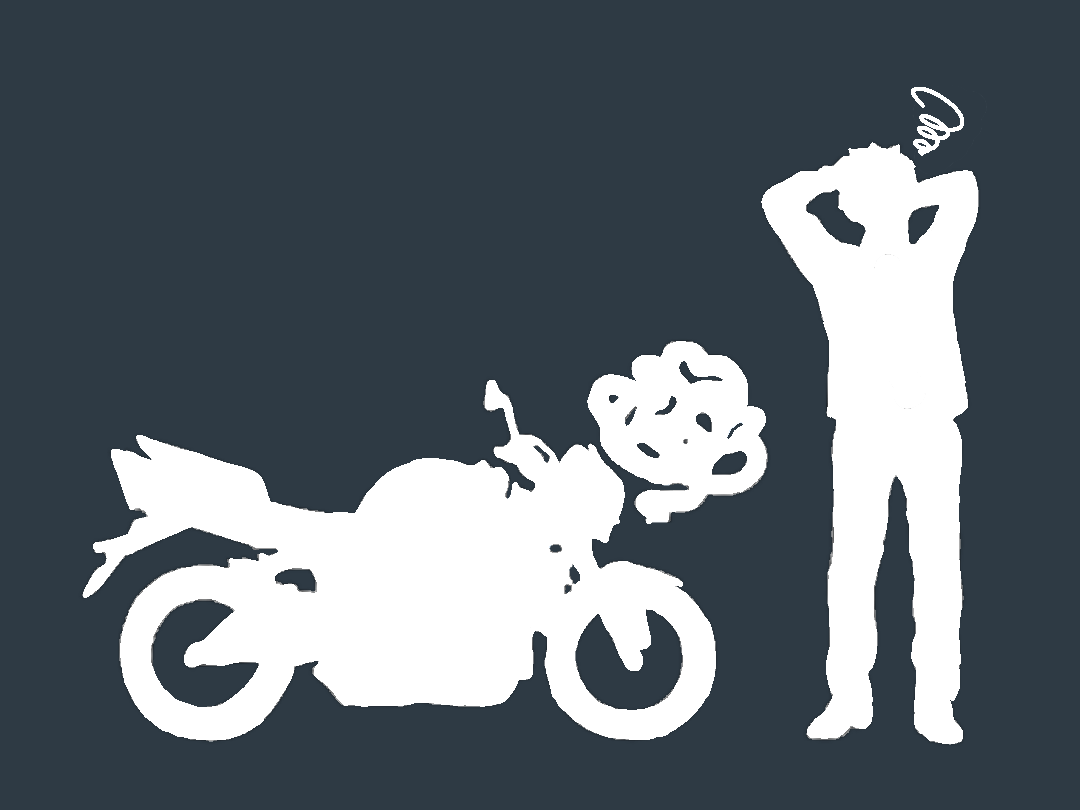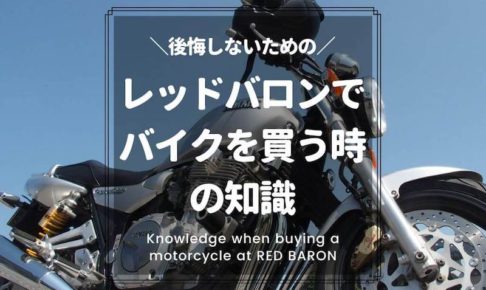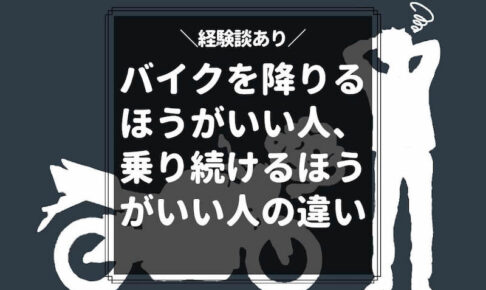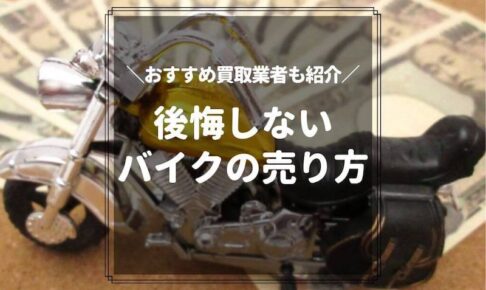- バイクに乗りたいんだけど…
- 何から始めればいいかわからない
- 本当に必要な手順と知識だけを学びたい
バイクを始めようとした初心者が「結局何から始めればいいの?」と最初の一歩で挫折してしまうケースは非常に多いです。
僕はバイクに10年以上乗ってきて、今は楽しいバイクライフを送っています。しかし初心者のときは、知識不足のため何度も失敗し、たくさんの遠回りをしてきました。
そこでこの記事では、初心者でも迷わずにバイクを始められるように『手順と基礎知識』をまとめて解説します。
この記事を読めば「ゼロから始める初心者がバイクに乗り出すまでに本当に必要なこと」が全て分かります。
バイク免許を取る
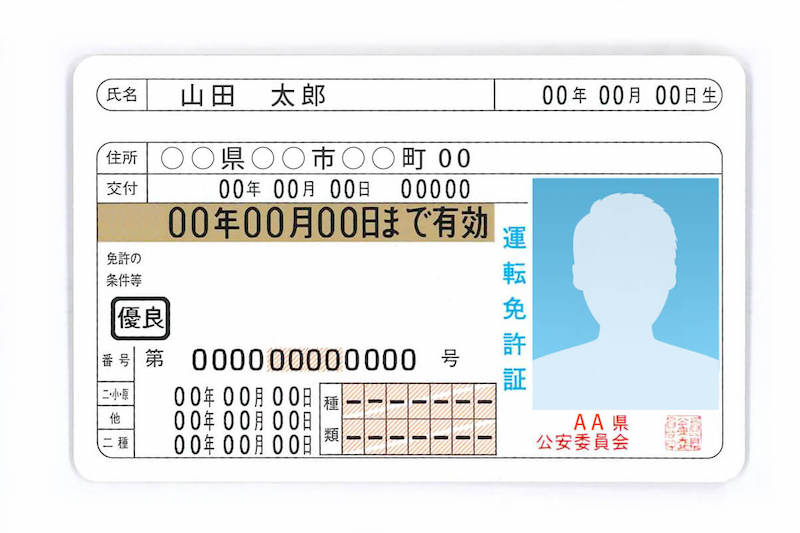
とにもかくにも、免許がないと始まりません。
まずはバイク免許に関する4項目について解説します。
- バイク免許の種類と特徴
- 免許の取り方
- 免許取得までの費用
- 免許取得までの時間
①バイク免許の種類と特徴

バイク免許にはいくつか種類があります。
種類と特徴を確認して、必要な免許を取得しましょう。
原付免許
排気量が50ccまでのバイクに乗れます。
学科試験のみで免許が取得できます。また、普通自動車免許を持っていれば、その免許で原付バイクに乗れます。
利便性は高いですが、30km/hの速度制限や二段階右折などの交通規制が設けられていることは知っておきましょう。
小型限定普通二輪免許
排気量が125ccまでのバイクに乗れます。
原付バイクとの大きな違いは、2人乗りができることと、AT限定免許が用意されていることです。
普通二輪免許
排気量が400ccまでのバイクに乗れます。
小型限定普通二輪免許で乗れるバイクとの大きな違いは、高速道路を利用できることです。
大型二輪免許
全てのバイクに乗れる、排気量制限なしの免許です。
取得可能年齢は18歳以上です。(大型二輪以外は16歳以上)
大型二輪の魅力は、「大型二輪免許は取得すべき?大型バイクに乗ると感じられる魅力を徹底解説!」で詳しく解説しています。
僕のおすすめは次の2つです
- 普通二輪免許
- 大型二輪免許
理由は、高速道路に乗れるから。行動範囲が広くなり、それだけツーリングを楽しめます。
迷ったらまず、普通二輪を選べばOKです。
②免許の取り方

バイク免許の取得方法は以下の2つです。
- 教習所で取得する
- 一発試験で取得する
一発試験は教習所を利用しない方法で、運転免許試験場などで直接試験を受けます。
メリットは、すんなり合格できれば教習所に通う時間と費用を節約できる点ですが、何度やっても合格できないリスクがあります。
なので、確実に免許を取得したい場合、教習所を利用しましょう。
できる限り短期間かつ低価格で取得したい場合は、合宿を利用する方法があります。
合宿は場所によって料金やサービスが変わるので、損をしないために下記のサイトでよく比較検討をしてください。
【比較サイト】③免許取得までの費用

「免許取得までどれだけの費用がかかるの?」という人に向けて、少し解説しておきます。
普通二輪免許の場合、費用は次の通りです。
- 普通車免許なし
- ・合宿の場合:12万円前後~
・通学の場合:14万円前後~ - 普通車免許あり
- ・合宿の場合:8万円前後~
・通学の場合:9万円前後~ - 一発試験
- ・2万5千円前後~
資金を準備する目安にしてください。
※費用を保証するものではありません。地域差が多分にありますので、大体の相場としてご覧ください
④免許取得までの時間
.jpg)
普通二輪免許の場合、必要な教習時限数は次のとおりです。
- 普通車免許なし
- ・技能:19時間
・学科:26時間 - 普通車免許あり
- ・技能:17時間
・学科:1時間
教習所に通学する場合、取得までの日数は混雑状況に大きく左右されます。
スムーズに受講できれば1ヶ月程度ですが、繁忙期であればそれ以上かかることも珍しくありません。事前に確認しておきましょう。
まとまった時間が確保できるのであれば、取得までのスケジュールが立てやすい合宿を利用するのも手です。
繰り返しにはなりますが、合宿先は比較サイトを利用してお得なものを選びましょう。
【比較サイト】バイクを選ぶ
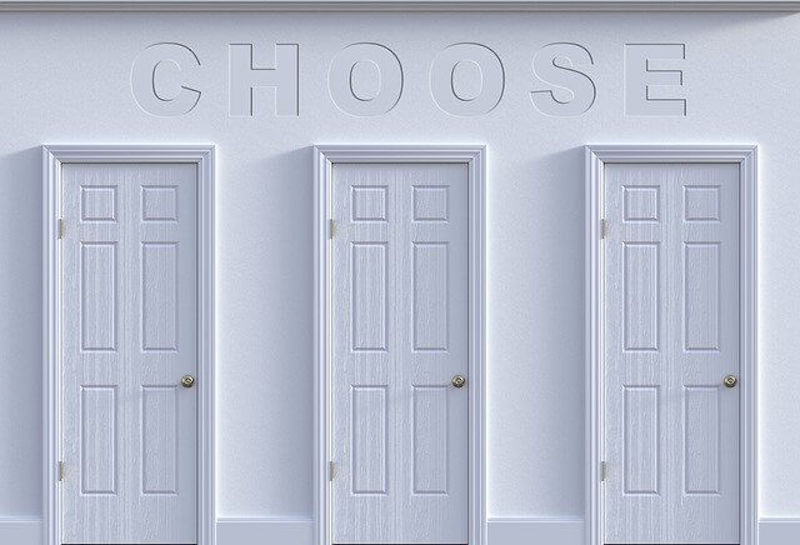
免許取得の段取りがついたら、バイクを選びます。
バイクは種類が多く、それぞれに特徴があります。あなたに合った一台を見つけるために、必要な知識を解説します。
- バイクの種類と特徴
- バイクの選び方
バイクの種類と特徴

バイクは次の3種類に大別されます。
- オンロードモデル
- 舗装された道路を走ることが想定して作られているバイクです
- オフロードモデル
- 舗装されていない道路を走ることができるバイクです
- スクーター
- オートマチックタイプなので比較的運転がラクなバイクです
バイクといえば、一般的にオンロードモデルとオフロードモデルを指すことが多いので、この2種類についてより詳細な種類と特徴を解説します。
ネイキッド
ネイキッドは、カウルなどがないシンプルな構成のバイクです。
特徴は以下のとおり。
- 教習所で使われることが多く、圧倒的な乗りやすさが持ち味
- カウルがないので、風の影響を受けやすい
初心者や正統派なバイクが欲しい人におすすめです。
ネイキッドの魅力を詳しく知りたい場合は、以下の記事をお読みください。
【参考】自分の直観を信じて選ぼう!僕がネイキッドバイクに乗り続ける5つの理由
ツアラー
ツアラーは、長距離を快適に移動することを目的に開発されたバイクです。
- 風を防ぐカウルや電源、グリップヒーターなどの快適装備が付いている
- 排気量が大きいモデルが多い
- 装備が充実している分、車体が重くなる
長距離ツーリングを快適に楽しみたい人におすすめです。
例)FJR1300、GSX1300R
スーパースポーツ
スーパースポーツは、速く走ることに特化したバイクです。
- 加速やコーナリング性能が高い
- カウルが付いているモデルが多く、風の影響を受けにくい
- ライディングポジションが前傾なので、長距離ツーリングでは疲労しやすい
とにかく速く走りたい人におすすめです。
例)YZF-R1、ZX-6R、CBR1000RR
クルーザー(アメリカン)
クルーザーは、低くて長い車体、ドコドコというエンジン音が特徴的なバイクです。
- ゆったりとした乗車姿勢がラク
- バンク角が浅いので、カーブはやや苦手
独特なエンジン音や外観が好きな人、高速道路などの直線を主に走る人におすすめです。
例)ドラッグスター400、Shadow AERO
トレール
トレールは、オフロードモデルの中でも、特に林道や荒れた道などの走行に特化したタイプです。
- オンロードモデルでは入れないような道も走れる
- 車体が軽いので、取り回しが簡単
- 車高が高くて車体が軽いので、高速道路で長距離を走るのには向かない
バイクで林道なども走りたい人におすすめです。
例)セロー250、XR230
アドベンチャー
アドベンチャーモデルは、長距離を快適に走ることができ、少し道が悪くても走れるバイクです。
- 積載性能が高い
- 多少の荒れた路面でも走れる
多少のダートも想定した長距離ツーリングがしたい人におすすめです。
例)CRF250、R1200GS
バイクの選び方

ここでは後悔しないバイク選びのコツを解説します。
- 外観と目的で選ぼう
- 排気量の違いは要チェック
- 中古で選択肢を広げよう
- 迷ったら250ccを買おう
①外観と目的で選ぼう
バイクにおいて外観はとても重要だと考えています。
「あ、このバイクかっこいい!乗りたい!」という直感を大切にして選ぶと、失敗しにくいです。見た目が気に入っていれば、欠点ともうまく付き合える可能性がぐっと上がりますからです。
次に目的です。「バイクに乗って何がしたいか?」ということですね。
気軽に乗るならネイキッド、速さを求めるならスーパースポーツを候補にする、みたいな感じです。
他人の選び方を参考にしたい場合、僕の例を「バイクはどれを選べばいい?後悔しないバイクの選び方」で詳しく解説しています。
②排気量の違いは要チェック
バイクは排気量でも特徴が異なります。
僕が今まで乗ってきたバイクを排気量別の特徴でまとめると以下のとおり。
- 250cc
- ・維持費が安い(車検がない)
・燃費が良い
・車体が軽い
・加速力が弱い
・長距離ツーリングで疲労が溜まりやすい - 400cc
- ・絶妙なパワー感
・アクセルを開けて楽しめる
・維持費は大型バイクと大差ない - 1300cc
- ・圧倒的な存在感と所有感
・絶大なパワー
・気軽に乗れるとは言い難い
どれが一番良いとかではなく、自分の目的に合った排気量を選ぶのが大切です。
実例付きで排気量の違いを知りたい方は、以下の記事を読んでください。
【参考】排気量によるバイクの違いを徹底比較!250・400・1300㏄に乗ったからわかった!
③中古で選択肢を広げよう
中古バイクは以下のような魅力があります。
- 生産終了車など選択の幅が広がる
- 新車よりも安価な場合が多い
とにかく選択の幅がぐーんと広がるので、中古バイクは良い選択肢の一つだと考えています。
「すぐ壊れない?」、「修理代で逆に高くなるのでは?」と心配かもしれませんが、きちんと選んでしっかりメンテナンスすれば、中古バイクでも大きなトラブルなく乗り続けることができます。
なぜそう言い切れるかというと、僕自身が3台の中古バイクをトラブルなく乗ってきたからです。全て20年落ちの状態で入手し、平均で2万キロ以上ずつ乗りましたが、困ったことはありません。
トラブルなく中古バイクに乗るコツは、「中古バイクの不安解消!選び方、メンテナンス、トラブル対処法【20年落ち3台に乗った結論】」で詳しく解説しているので参考にしてください。
④買いたいバイクが決まらない場合
自分が乗りたいバイクに乗るのが一番です。でもそれが見つからない場合、バイク選びが辛いものになりかねません。
そんな人に向けて僕ができるアドバイスは、「まずは250ccを買って、徐々にステップアップしませんか?」ということです。
理由は以下のとおりです。
- 250ccが良い理由
- ・車体がコンパクトなので、乗ること自体が負担になりにくい
・車検がなく燃費も良いので、維持費が安い - ステップアップのメリット
- ・低リスクな状態で失敗して成長できる
・どの排気量にも魅力があることを実感できる
乗り換えのコストはかかりますが、それ以上に得られるものが大きいです。前述した中古バイクを利用すればコストも抑えられます。
「低リスクな状態で失敗して成長できるってどういうこと?」、「なんでどの排気量にも魅力があることを実感できるの?」と疑問に思った方は、「バイク選びで悩んだら250ccを買え!小排気量からのステップアップがおすすめな理由」をお読みください。
おすすめの250ccバイクは、ホンダのGB250クラブマンです。僕が乗っていたバイクで、乗りやすさと耐久性が抜群です。詳しくは、以下の記事にまとめています。
【参考】【ホンダが誇る名車】GB250クラブマンの魅力を徹底解説
バイクを買う

いよいよバイクを買う段階です。
高額な買い物なので後悔しないように、この章で必要な知識を学んでおきましょう。
- バイクショップの選び方
- バイクの買い方
バイクショップの選び方

バイクを買うにあたり、まず重要になるのがショップ選びです。
理由は以下の2点。
- 購入時のトラブルを少なくするため
- バイクに乗り続けるにはショップのアフターサービスが重要だから
そのため、バイク初心者は個人オークションやフリマアプリの活用はあまりおすすめできません。
まずは信頼できるショップを見つけましょう。
信頼できるショップの見つけ方
信頼性だけで言えば、正規販売店(ディーラー)が最も安定しています。
見分けが難しいのは個人経営のショップ。身近な人の紹介があれば幾分か安心ですが、そんなに都合よくはいかないものです。
というわけで、インターネットなどで評判を比較することになります。評判が良さそうなショップを見つけたら、必ず訪問してください。店の人と話しながら、ショップ全体の雰囲気を肌で感じて、信頼できるかどうかを見分けるしかありません。
また、保証システムの有無やサポート体制もショップによります。よく比較して事前に確認してください。
バイクの買い方

バイクとショップが決まったら、実際にバイクを買う工程です。
普段とは違う高額な買い物になるので、必要なものをショップと事前に打ち合わせしておくと安心です。
もれなく必要なのは以下の3点。
- 住民票(原本)
- 印鑑
- 現金(その他の支払い方法)
契約が完了すれば、あとは納車を待つのみです。この期間のワクワク感を大いに楽しみましょう!
僕は、転勤があるので全国展開のレッドバロンを利用しています。レッドバロンでバイクを買った時の流れは、「必見!レッドバロンでバイクを購入するときに役立つ7つの知識」で詳しく解説しています。
バイク購入時は「車両本体価格」とは別に、「整備手数料」「各種税金」などの費用が発生します。
『乗り出し価格』はその全てを合わせたもので、実際に支払う金額となります。予算オーバーとならないように注意してください。
バイク保険に加入する

バイクに乗るなら保険について無知ではいけません。
必要最低限の知識と任意保険の重要性を解説します。自賠責保険も任意保険も必ず加入しましょう。
バイク保険には2種類あります。
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
- 任意保険
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
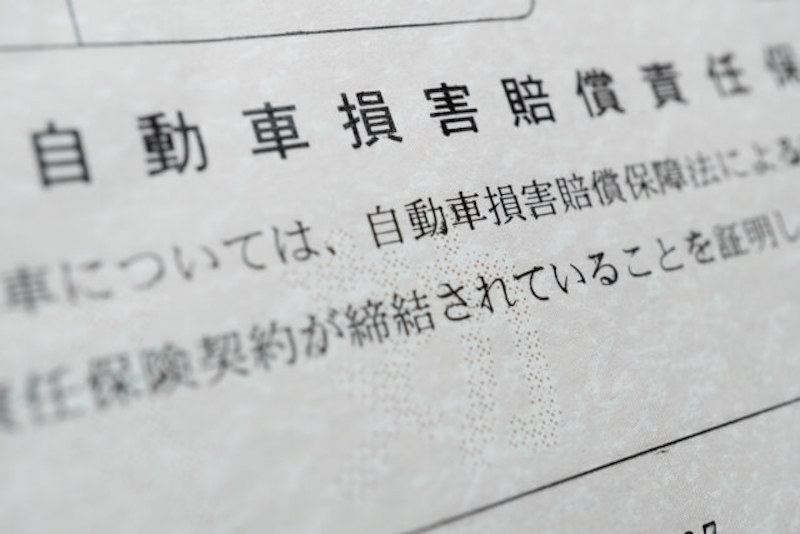
原付から大型バイクまで、ナンバーのついた(公道走行前提)車両は全て、加入が義務付けられています。
自賠責保険に加入せず運行した場合は、事故を起こさなくても1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となるので、忘れずに加入しましょう。
さらに知っておくべきは、補償内容です。
適用されるのは人身事故だけで、傷害で120万円、死亡に対しては3,000万円、重度後遺障害に対して4,000万円という限度額があります。
「加入者自身の傷害」と「車やぶつけた建造物などのモノへの損害」は、自賠責保険の対象外。
万が一事故を起こして、次のような支出が発生すれば高確率で人生が詰みます。
- 賠償金が限度額以上となった場合(1億円以上となるケースもある)
- 自身の傷害に対する支出
- 車やぶつけた建造物などのモノに対する損害賠償
これに備える必要がないのは数億円規模の資産のある大富豪くらいですが、僕も含めそんな人は少数です。
だから、任意保険に加入して備えておく必要があるのです。
任意保険

任意保険で補償される代表例は、以下のとおりです。
- 対人賠償保険:事故相手のケガに対する補償
- 対物賠償保険:事故時に破損した車や建造物など、「モノ」に対する補償
- 人身傷害保険:事故時に搭乗中の人が死傷した場合に、その実際の損害額を補償
- 搭乗者傷害保険:事故時に搭乗中の人が死傷した場合に、定額で補償
- 車両保険:加入者の契約車両が損害を受けた際に、補償
最低でも、対人賠償保険と対物賠償保険を無制限で補償してもらえるプランに加入しておきましょう。
僕の任意保険に対する考え方
対人賠償保険と対物賠償保険を無制限にする以外はそこまで重要視していません。自身の死傷に対する補償は別で備えます。車両保険も高価な新車以外は不要だと思っていて、万が一の際は貯金で支出するスタイルです。
ただし、これは個人的な見解なので、プランについては自身でご判断ください。
結論、自賠責も任意保険も確実に加入しておきましょう。
任意保険は会社によって同じ補償内容でも料金が異なります。下記のような一括比較サイトを利用して、損をしないように選んでください。
現時点で僕が任意保険に加入するなら、チューリッヒのバイク保険を選びます。
【任意保険の一括見積もりサイト】バイク保険一括見積もり
バイク用品を揃える

バイクに乗るにあたり、最低限必要なものは4つです。
- ヘルメット
- グローブ
- ジャケット
- シューズ(ブーツ)
僕が愛用しているブランドは以下のとおり。少々値が張るものもありますが、質は間違いない商品が揃っています。
- ヘルメット:Arai(アライ)
- グローブ:JRP
- ジャケット:SIMPSON(シンプソン)
- ブーツ:ワイルドウィング
その他、愛用のバイク用品は、下記の記事にまとめています。
10年以上(距離にして7万km以上)のバイク歴で実際に使用して、本当に良い物だけを厳選しました。詳細なレビュー記事も揃えていますので、参考にしてみてください。
【参考】おすすめのバイク用品まとめ!実際に愛用している厳選グッズ10選!
最後に:バイクは魅力が盛りだくさん

初心者でも迷わずにバイクを始められるように、という気持ちを込めて『手順と基礎知識』をまとめて解説してきました。
最後にバイクの魅力を紹介して終わります。
- 乗っているだけで楽しい
- 体調が良くなる
- 移動時間が楽しめる
- グルメを堪能できる
- 絶景に出会える
- 人との出会いがある
- 危険予知能力が身につく
- 心の保養になる
- 地図のスキルが身につく
- 心と体が若返る
- フットワークが軽くなる
- 駐車場所に困らない
- 一人の時間を楽しめる
- 他の趣味と組み合わせて楽しめる
上記で「なぜ?」と思うものがあれば、「バイクに乗るメリットは14個!僕が10年以上も乗り続けている理由をまとめました。」で詳しく解説しています。
免許取得からバイクの購入、保険の加入までやることがたくさんあって嫌になったかもしれません。でも、それをやり切ってバイクに乗り始めたら、素晴らしい経験が待っています。
まずは免許取得の段取りから初めてみてください。
このブログではバイクに乗った後も役立つ情報をたくさん発信していますので、ブックマークをして定期的に訪れてくれると嬉しいです(^ ^)
お互い素敵なバイクライフを送りましょう!
旅のトラブルに備えたいならJAFがおすすめ!

車やバイクで遠出をするとなれば、万が一のトラブルが心配。
だから、僕は10年以上ずっとJAF会員です。
- バッテリー上がり
- パンク対応
- ガス欠対応
- 故障車けん引
これらが全て24時間365⽇、何度でも、無料で対応。安心してツーリングに集中できます。
さらに、身近なお店(全国約39,000の会員優待施設)でJAF会員割引や優待が受けられるので、年会費は実質無料。
お得に安心を手に入れましょう!
\僕もJAF会員です(^ ^)/